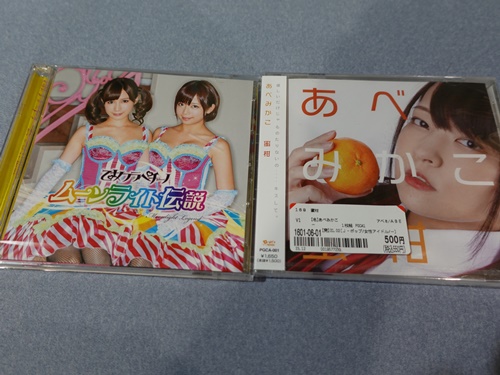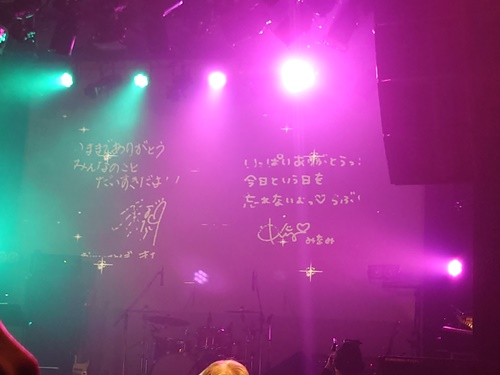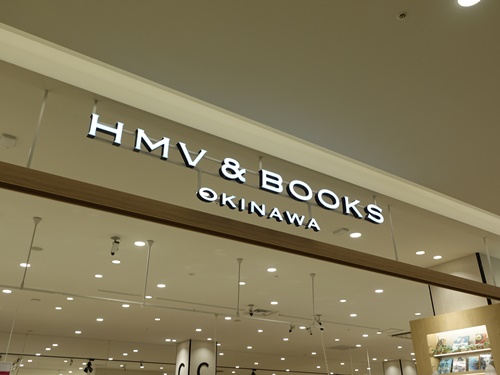本日、新星堂 アトレ吉祥寺店が来月の5月19日に閉店することが発表されました。

【閉店のお知らせ】
— 新星堂 アトレ吉祥寺店 (@ssd_kichi) April 19, 2024
いつも新星堂アトレ吉祥寺店をご利用いただき
誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら当店は2024年5月19日(日)をもちまして
閉店させていただく運びとなりました。
長らくご愛顧いただきました皆々様に
心から厚く御礼申し上げます。
新星堂アトレ吉祥寺店 スタッフ一同 pic.twitter.com/dsb5Sr0GeJ
新星堂は元々高円寺の小さな個人店舗から始まり、1964年に法人化してからかなりの期間において荻窪に本社を置いていたこともあり、ホームグラウンド的な地域として中央線沿線には多くの支店が置かれておりました。
それがアトレ吉祥寺店の閉店をもって、中央線沿線の新星堂が全て閉店と相成ります、ということで。
以下、中央線沿線に過去存在した新星堂の一覧。年月日は閉店日。さすがに20世紀のことの詳細はわからず、店が存在していましたよ、ということだけ。
19??/XX/XX:新星堂 吉祥寺店(ニューマルイ内)
19??/XX/XX:新星堂 立川店(中武デパート内)
19??/XX/XX:新星堂 八王子店(路面店)
19??/XX/XX:新星堂 八王子ニューマルイ店(東京都八王子市)
199?/XX/XX:新星堂 荻窪店(東京都杉並区)
199?/XX/XX:新星堂 荻窪タウンセブン店(東京都杉並区)
2004/02/29:新星堂 中野丸井店(東京都中野区)
2004/06/10:新星堂 八王子駅ビル店(東京都八王子市)
2004/07/20:新星堂 高円寺北口店(東京都杉並区)
2007/06/12:新星堂 CD SHOPアポロ店(東京都立川市)
2007/07/23:新星堂 西国分寺店(東京都国分寺市)
2009/09/01:新星堂 小金井店(東京都小金井市)
2010/01/24:新星堂 高円寺レコード店(東京都杉並区)
2010/01/31:新星堂 西荻窪店(東京都杉並区)
2012/07/29:新星堂 天沼店(東京都杉並区)
2012/07/31:新星堂 荻窪ルミネ店(東京都杉並区)
2013/02/24:新星堂 八王子東急スクエア店(東京都八王子市)
2016/03/31:新星堂 西八王子店(東京都八王子市)
2021/08/31:新星堂 阿佐ヶ谷店(東京都杉並区)
2023/01/22:新星堂 ルミネ立川店(東京都立川市)
2023/09/30:新星堂 武蔵境ヨーカドー店(東京都武蔵野市)
2024/01/31:新星堂 国分寺駅ビル店(東京都国分寺市)
2024/05/19:新星堂 アトレ吉祥寺店(東京都武蔵野市)
新星堂は2006年頃には経営不振でにっちもさっちもいかなくなり、TSUTAYAと提携したはいいもののシステム投資に耐えられずに解消したり、光通信と提携したはいいものの狭い店舗内でスマホも売ろうとしてうまくいかずに解消したりした末に、WonderGOOを運営するワンダー・コーポレーションに吸収されました。
が、その段階でワンダーコーポレーションは茨城県拠点のスーパーマーケットチェーンカスミの子会社でしたので、新星堂もカスミグループの一員となり、本社も荻窪からつくば市の郊外に移転し、荻窪の本社の土地は売られて現在マンション。
その後、2018年にすごい勢いでいろんな企業を買収していたRIZAPに買われ、その後いろいろ整理されて、現在の新星堂はREXTという企業の中のブランドのひとつ、という位置付けです。
RIZAP直後くらいまでは、そこまで閉店も多くなく踏ん張っている感があったのですが、そういう立場になってしまったらもう社内の「維持しよう」という意志の力もさほど大きくなりにくい、ということではないかなあ、と思っています。
というか新星堂、別に中央線沿線だけ店舗がなくなっているわけでもなく、東京都内に残る店舗は葛西と昭島の2店舗のみ(秋葉原の「エンタバ」業態は除く)。
一方、新星堂が全滅する中央線沿線にどれだけのCD店が残存しているかと考えてみたところ、タワーレコードは吉祥寺も八王子も既に閉店し、もちろん個人経営店舗ももうない。中古盤屋は割とありますが、普通にふらっとヒットチャートの新譜を買って帰れるCD店は新宿を出たらもう現存するのは立川のHMVだけのはず。
中野ブロードウェイに演歌なら買える店、テクノ系なら新譜も多少買える店はあり、吉祥寺のHMVはアナログ中心だけど多少新譜CDも置いてあったはず。あと吉祥寺と立川のディスクユニオンもある程度新譜も扱っていますが、いずれもあんまり普通のCDショップとは言えない感じで。
西八王子のミチル楽器は移転してまだやっているのかな。ここも演歌系だけど。
そんな感じで、東京もこんなもんです。
まあ、地方ではロードサイドのTSUTAYAが閉店したら半径数十kmの範囲からCDを売っている店がなくなりました、みたいな地域ももはや珍しくなく、数百円払って電車に数十分乗れば渋谷や新宿の大型店に辿り着けるのは、まだありがたいのです。
つうか私は新宿勤めですので、帰りに寄れる。ありがたい。本当に最近は心からありがたい。
<追記>
八王子のJR駅ビルに山野楽器がありました。すみません。
また、裏が取れなかったので書きませんでしたが、一時期東中野駅周辺にも新星堂の店舗があったようです。